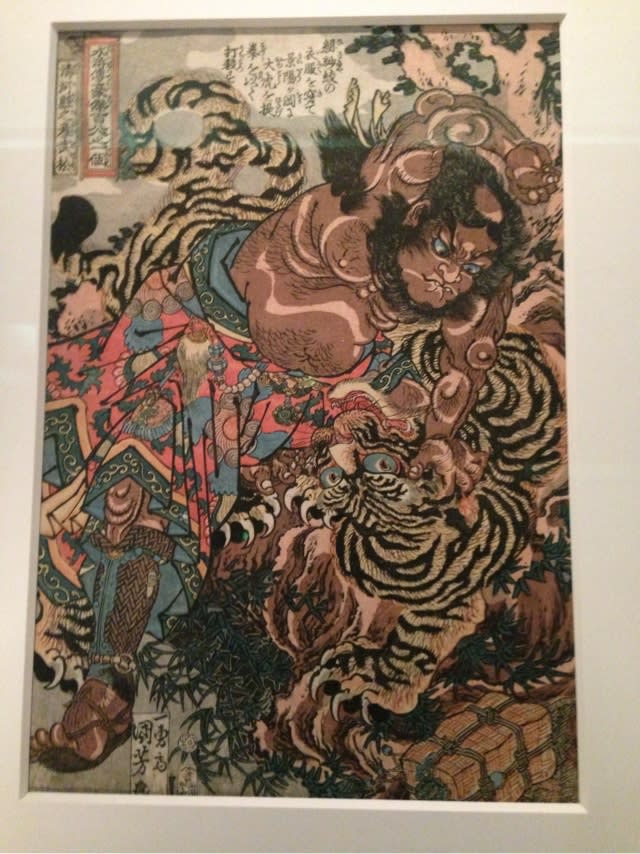文楽がの国立劇場公演には去年からご縁を頂いて
毎回の楽しみとなっています。
五月公演は
「公益財団法人文楽協会創立五〇周年記念
竹本義太夫三〇〇回忌記念」
という記念の公演となりました。
折良く、友人が竹本義太夫三百回忌記念の手ぬぐいをプレゼントしてくれました。
当日、演目の熊谷陣屋の応援として
埼玉熊谷市からゆるキャラの「ニャオざね」くんがきていました。
国立劇場のマスコット、くろごちゃんと一緒に会場入り口が
賑わっていました。
熊谷陣屋の熊谷は神戸須磨に設けられた熊谷直美の陣屋なのですが、
ここはゆるキャラ、ということのようでした。
一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)
熊谷桜の段
熊谷陣屋の段
並木宗輔を立役者とした全五段の時代物です。
宝暦元年(1751)に大阪豊竹座で初演されたそうです。
以来、歌舞伎でも人気の演目で知られています。
小次郎、敦盛の二人の母の心情、
義経に仕える直実、平家の武将への恩義、等々が絡み合い、
結局、直実は小次郎を失った悲しみと無常を抱えて出家していくのでした。
高麗屋、幸四郎の「夢だぁ〜」と泣く泣く花道を下がる有名なシーンを思い出します。
近松門左衛門生誕三六〇年記念
曾根崎心中(そねざきしんじゅう)
生玉社前の段
天満屋の段
天神森の段
近松の心中物、曾根崎は近松が51才で竹本義太夫のために書いた作品で、
元禄16年(1703)大阪竹本座で上演され、大当たりをとります。
初演後、上演が途絶えますが、昭和30年に復活され、
現在では人気演目となっています。
この昭和30年で復活という説明を鑑賞ガイドで知って驚きます。
醤油屋の徳兵衛と遊女お初のどうにもならない心中、という結末は
あわれ、若い二人の恋の道の純情とともに甘い陶酔へと導きます。
「此の世の名残、夜も名残。死にゆく身をたとふれば
あだしが原の道の霜。一足づつに消えてゆく
夢の夢こそあはれなれ・・・・・」
なんとも名調子の語りが謡われます。
去年からのご縁で東京公演は昼間の部をずっと鑑賞してきました。
といっても年に数回ですから、まだまだ始まったばかり。
遠い、二十代の頃に国立劇場で観ていますが、何を観たのか忘却の彼方。
それでも、舞台横での三味線と大夫の語りの迫力に圧倒されました。
次回は9月だそうで、またまた楽しみにします。
お代は歌舞伎座の3階席くらい。
パンフレットが600円で床本集(台本のようなもの)が付録について
充実の内容。毎回コレも楽しみ。
某、大阪のえらいかたによる大波で、文楽協会は大激震。
そんなこともあったけれど、こんな楽しいライブが命たたれてなるものか、
五月公演は大入りも出たようで、なによりなによりです。
今後も文楽の活動に微力ながら応援エールかけていきたいと思っています。
ゆるキャラのニャオざねとくろごちゃんは
こちら〜
![]()
毎回の楽しみとなっています。
五月公演は
「公益財団法人文楽協会創立五〇周年記念
竹本義太夫三〇〇回忌記念」
という記念の公演となりました。
折良く、友人が竹本義太夫三百回忌記念の手ぬぐいをプレゼントしてくれました。
当日、演目の熊谷陣屋の応援として
埼玉熊谷市からゆるキャラの「ニャオざね」くんがきていました。
国立劇場のマスコット、くろごちゃんと一緒に会場入り口が
賑わっていました。
熊谷陣屋の熊谷は神戸須磨に設けられた熊谷直美の陣屋なのですが、
ここはゆるキャラ、ということのようでした。
一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)
熊谷桜の段
熊谷陣屋の段
並木宗輔を立役者とした全五段の時代物です。
宝暦元年(1751)に大阪豊竹座で初演されたそうです。
以来、歌舞伎でも人気の演目で知られています。
小次郎、敦盛の二人の母の心情、
義経に仕える直実、平家の武将への恩義、等々が絡み合い、
結局、直実は小次郎を失った悲しみと無常を抱えて出家していくのでした。
高麗屋、幸四郎の「夢だぁ〜」と泣く泣く花道を下がる有名なシーンを思い出します。
近松門左衛門生誕三六〇年記念
曾根崎心中(そねざきしんじゅう)
生玉社前の段
天満屋の段
天神森の段
近松の心中物、曾根崎は近松が51才で竹本義太夫のために書いた作品で、
元禄16年(1703)大阪竹本座で上演され、大当たりをとります。
初演後、上演が途絶えますが、昭和30年に復活され、
現在では人気演目となっています。
この昭和30年で復活という説明を鑑賞ガイドで知って驚きます。
醤油屋の徳兵衛と遊女お初のどうにもならない心中、という結末は
あわれ、若い二人の恋の道の純情とともに甘い陶酔へと導きます。
「此の世の名残、夜も名残。死にゆく身をたとふれば
あだしが原の道の霜。一足づつに消えてゆく
夢の夢こそあはれなれ・・・・・」
なんとも名調子の語りが謡われます。
去年からのご縁で東京公演は昼間の部をずっと鑑賞してきました。
といっても年に数回ですから、まだまだ始まったばかり。
遠い、二十代の頃に国立劇場で観ていますが、何を観たのか忘却の彼方。
それでも、舞台横での三味線と大夫の語りの迫力に圧倒されました。
次回は9月だそうで、またまた楽しみにします。
お代は歌舞伎座の3階席くらい。
パンフレットが600円で床本集(台本のようなもの)が付録について
充実の内容。毎回コレも楽しみ。
某、大阪のえらいかたによる大波で、文楽協会は大激震。
そんなこともあったけれど、こんな楽しいライブが命たたれてなるものか、
五月公演は大入りも出たようで、なによりなによりです。
今後も文楽の活動に微力ながら応援エールかけていきたいと思っています。
ゆるキャラのニャオざねとくろごちゃんは
こちら〜