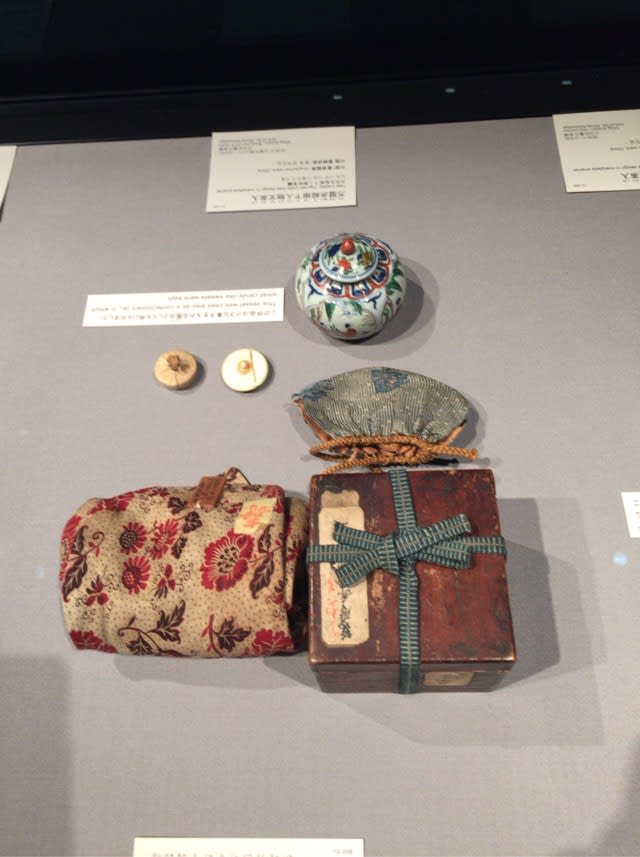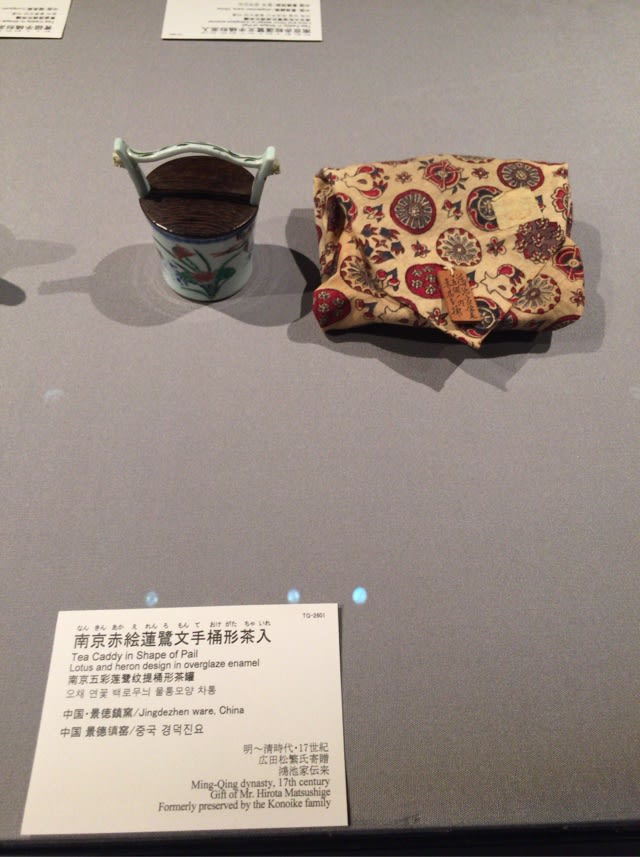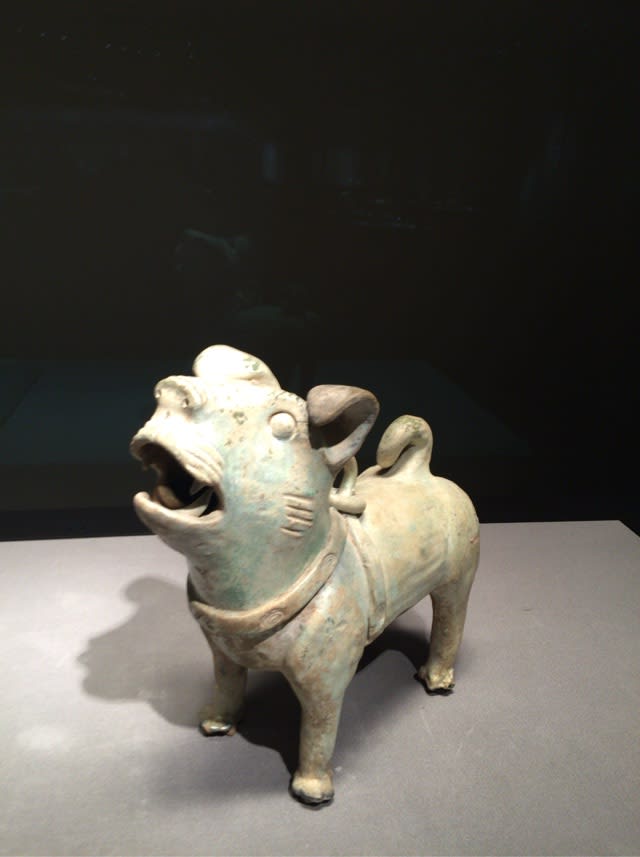年末恒例のアート鑑賞のベストテンを挙げようと思いつつ、
年が明け、松が取れてしまいました。
遅まきながら、2015年を振り返りたいと思います。
2015年は特別な一年でしたので、
行動範囲が限られていて、至近距離の美術館ばかりでした。
数年来の中で一番少ない展覧鑑賞となりましたが、
美しくも麗しい芸術品を見ることができました。
アート鑑賞の他では、文楽は東京公演はほとんど見に行くことができましたし、
六本木文楽では最後の玉女さんの人形遣いを拝見し、
その後、国立劇場で玉男襲名というおめでたい熊谷陣屋では
パワフルで凛々しい熊谷を拝見しました。
歌舞伎界では中村雁治郎襲名もありました。
父上の藤十郎さん、ご子息の壱太郎さん三代そろっての
おめでたい吉田屋をお芝居中に襲名披露の場面もあって、
賑々しい雰囲気のなか楽しんで観てきました。
藤十郎さんの和事をさらりと継承するお茶目でさわやかな雁治郎さんに
なるのではと期待しています。
それにしても濃厚な血流です。
今年は歌舞伎界の襲名ラッシュ、橋之助さん、芝雀さん、おめでとうございます。
襲名披露舞台の無事をひたすらに祈念します。
では、アートランキング、はじめます。
10 スサノヲの到来 いのち、いかり、いのり展 渋谷松濤美術館
実は改装してから初めての訪問となりました。
スサノヲ展に御贔屓の木彫作家、佐々木誠さん作品が出品することを
ご本人からご案内を頂戴していまして、
その展覧の巡回展をずっと伺えないまま申し訳なく思っていました。
川村美術館での展示にはカナリ期待していましたので、
ますます動きの取れない状況があって残念でしたが、
ようやく、ようやくラストの松濤に間に合ったことが印象に残っています。
「スサノヲ」を日本古来からどう表現してきたのかを
縄文から現代の今までを多岐にわたっての展覧でした。
その展示をどう受け止めて良いのやら、途方に暮れましたが
図録にそれが美しく解説されていましたので、
それを頼りにしようと思いました。
民俗学的展覧としても珍しい取り組みだったのではないでしょうか。
もちろん佐々木誠さんの「八挙須」(やつかひげ)
その圧倒的存在は群を抜いていました。
また、「深鉢突起破片」縄文中期のものは
市川で大変お世話になった宗左近氏旧蔵のもので、
「有が無をうんだ」と宗氏が実例として上げたもので、
実見できた大変感慨深いものでした。
足利市立美術館、DIC川村記念美術館、北海道立函館美術館、
山寺芭蕉記念館、渋谷区立松濤美術館を
2014年10月18日~2015年9月21日の間巡回していました。
図録の出来が大変秀逸で、何度見ても読んでも太い根源がつまっています。
9 ダブルインパクト明治のニッポンの美 東京藝術大学大学美術館
(ボストン美術館×東京藝術大学)
明治開国時代の日本の美術工芸は今見ても飛び抜けて変なパワーが
噴出しています。おどろおどろしいというのか、熱狂しているというのか、
盛り過ぎ、やり過ぎ過多で、そこにこそ日本の美術技術工芸をアピールすべき
王道があったのでしょう。
この狂乱の時代に生まれた超絶技巧芸術にひれ伏し、ため息をもらします。
とはいえ、好物の作品ラッシュでただそれだけで嬉しくもわくわくした
展覧会でした。
ボストン美術館とのコラボで芸大コレクションと共鳴し合った
好企画でした。
ここから河鍋暁斎作品は一年をずっと引っ張り続けました。
鈴木長吉の突き抜けた「水晶置物」は狂気さえ感じるものでした。
江戸から明治を駆け抜けた柴田是真の画力確かな作品も秀逸でした。
そのなかで驚きを持って鑑賞したのは
横山大観の「烏瓜に鳩」「月下の海」「海」
富士山の大観からは別物でした。
何という静けさ、情感のある透明感、こんな作品を
ボストン美術館が所蔵しているのでした。
日本の和様に西洋美術が乱入した結果、日本画の進むべき道が
紆余曲折してきた道程を見ることもできました。
橋本雅邦、狩野芳崖を見る度になぜか無理矢理
手法をディズニー化させられたような、切ない悲しみを感じてしまいます。
岡倉天心を初め、藝術大学創世の頃から明治を突き進んだ
日本の芸術家達の奮闘が会場中に熱気を渦巻き圧倒していました。
8 月映 東京ステーションギャラリー
この展覧企画が宇都宮美、和歌山県美、愛知県美、の巡回を経て
東京ステーションギャラリーで最後の展覧となりました。
そもそも「月映」(くつはえ)という木版画作品集を知ったのは
2008年うらわ美術館で開催された「誌上のユートピア」展で
陶酔の誌上、詩情、デカタンの極みをドキドキもので鑑賞した時に
「方寸」と共に展示されたことからでした。
「詩情のユートピア」の図録が大変美しかったのを現美の
図書室で見て、どっきりしまして、絶対に巡回する
うらわに行かねばと思ったのでした。
以来、そこに取り上げられている作家たちを注視ししてます。
浮世絵から継承されてきた版画というジャンルに
まったく異次元の版画が生まれた1900年初頭に
文芸誌とのコラボで新作品を発表してきた作家たち、
田中恭吉、藤森静雄、恩地幸四郎。
その三人が精神の純粋と信仰、親交のひたむきな姿が
「月映」として集結しました。
東京ステーションギャラリーの醸し出す煉瓦の壁が展示作品と共鳴し合って
短命だった田中恭吉の思いがますます迫ってきました。
「月映」刊行百年記念として研究成果の発表となったそうです。
恭吉の筆跡がとても緻密で真面目でフォントがあるかのように
整然としていたことにも驚かされました。
作り出された版画の単純な線から、ついセンチメンタルな思いを
投げかけてしまいますが、センチになってもいいのだと、
三人の友情と純粋に跪くのでした。
図録は研究の素晴らしさのたまもの。珍しい作品をしっかり
カバーしてくれました。
「詩情のユートピア」と同じく、やはり図録はコギト制作でした。
この中の恩地幸四郎の個展が今年東京国立近代美術館で
もうすぐ、1月13日からの開催で、
これまた大変に楽しみにしているところです。
2015年のステーションギャラリーは鴨居玲展、九谷展
など、好企画続出でした。
7 これからの美術館事典 国立近代美術館
(国立美術館コレクションによる展覧会)
この展覧会の企画が大変興味深かったので、7位にランクインしました。
美術展といえば、個性的な、著名な、芸術家か、海外の美術館出品か、
特定の時代とか、ジャンルとかに焦点をあわせるものですが、
この展覧は近美のコレクション展。
会場に所狭しと所蔵品が様々な切り口でシャッフルされて
鑑賞者との距離をぐっと身近にさせる工夫が詰まっていました。
美術館所蔵品による,博物展のような具合でした。
切り口となったキーワードは事典を引くように並べられ、
簡易見取り図に現れました。
そういった丁寧な案内図を参考になどしないまま、
ずんずん気になったものだけを追いかけて見てきましたが、
会場内が様々に仕掛けられているので、アミューズメント化した
見世物として大変愉快に写メをしたりしながら回りました。
舞台裏としての収蔵庫の中を表現した調査研究のパートが
特に興味深かったです。
今年は藤田嗣治を随分取り上げられましたが、
近美といえば、藤田嗣治の個展を開催し脚光を浴びたことがあり、
あの展覧会場の熱気たるや、近美でのあの混雑はなかなか体験したことがありません。
その藤田の作品が研究され、大切に保管される様子に
藤田嗣治という画家のセンセーショナルな存在が
一段ともの悲しく映ったのでした。
その後の藤田の戦争画特集を見に行けず、残念でした。
ともあれ、この展覧会を企画した勇気みたいなものに
よくぞやってくれた、と拍手を送りたくなったのでした。
勿論オレンジ鮮やかな図録も楽しめるものでした。
こういう、意外性をひっくり返して楽しむこと、大切だと思います。
6 大英博物館展 東京都美術館
(100のモノが語る世界の歴史)
そもそも工芸品が大好きなので、どんなモノが集まっているのかと
楽しみで行ったのですが、こんなに迫力有るものとは思いもかけず、
大英の心意気に尊敬を捧げたのでした。
人間はモノとのつきあいなしに生活は成り立ちません。
溢れるモノの歴史から大英がセレクトした100品目。
その視線の確かさと品格と未来をも見据える力に改めて
さすが大英、とうなってしまいました。
各章には世界地図があり、展示品がどこから来たのかを
導いてくれます。
日本からは嬉しい事に、縄文が並び、鏡、やきもの
北斎漫画、自在置物の蛇などが出品されました。
世界中の石、土、金属、角、紙などから生まれた
宗教的なモノ、生活グッズなどが文明、文化、民族、工芸の
発展と共に変化し、美しくかたどられてきたことを
世界を旅するように見て回る楽しさがありました。
銃のリサイクルで制作された「母」像が痛ましく、
世界中のどこかで今も銃を持つ人がいることの不幸と人間の犯す悪徳の連鎖、
それでも前を向かざるを得ない、人の性と芸術する宿命を感じ、心に刺さりました。
ラストには日本の建築家、坂茂さんの紙パイプの
災害避難用の間仕切りがセットされ、
それを最後にした展覧企画者の深い思いに胸をつかれたのでした。
自分が選ぶベスト5をハガキを求めて選ぶ楽しみもありました。
5 肉筆の浮世絵 美の競演展 上野の森美術館
すっかり年の瀬になって、もはやアート鑑賞は終わったかと思っていましたが、
ギリギリ自由時間が手に入って見てきたのですが、
本当に素晴らしすぎて仰天しました。
シカゴ ウェストンコレクションが日本初公開の
展覧をしていたのですが、うっかり、ノーマーク。
アメリカの浮世絵ファン、侮れません。
国内で優品を見ていると思っている上から目線、反省しました。
会期はすでに後期となって、残念すぎました。前期も見たかった!!
シカゴのロジャー・ウェストン氏の所蔵肉筆浮世絵コレクションが
日本へ初里帰りを果たしているとのこと。
ご本人のご挨拶文からは日本美術品の収集は40年ほど前の事だそうです。
驚きです。当初は印籠を中心に収集しはじめ、
その展示に肉筆絵を使用してから肉筆絵の魅力に惹かれ、
収集を始めたそうですが、なんと1990年代後半なのだそうで、
いつしか百点を超えることとなったと、さらりと仰っています。
まだまだ収集可能な余地が残されているのでしょうか。
それなりの豊かな財源があればこそなのでしょうけれど、
シカゴの方が日本の美に魅せられてここまでの収集をされるとは
びっくりぽん、のひと言です。
すでに大阪、長野での展覧を終えて、上野の森美術館がラストのチャンスとなりました。
1月17日まで。未見の方、ぜひにとお勧めします。
浮世絵版画の事を思うと、肉筆浮世絵は高価な絵の具を使う一点ものでしょうから
当時も値が張るものだったことでしょう。
展覧は上方で展開した浮世絵、
江戸の開花、浮世絵諸派と京都西川祐信の活動、
錦絵の完成から黄金時代、百花繚乱・幕末の浮世絵界
上方の復活、近代の中で、という章立てからも上方にシフトしていることがわかります。
西川祐真、月岡雪鼎、祇園井特、岸駒、などの絵師の作品を
これほどの量で見るという幸いにワクワクさせてもらいました。
一点ものの肉筆画、微妙にバランスが変だったりするのですが、
どの美人画も着物の細やかさ、表情のしなやかさ、妖しさ、愛らしさが
ふんだんに盛り込まれていました。
懐月堂の線の太い強烈な肉筆画もシャープで迫力があって勢いがあります。
勿論、歌麿、北斎、などの巨匠も外していません。
今回、歌麿の肉筆画、それも仙人の姿の肉筆は珍しいのではないでしょうか。
新出とありましたので、もっとビッグニュースとして宣伝しても良かったと思います。
北斎の描く美人図の胸元の猫ちゃんはなんだか北斎描く
虎図に似ていて虎子、ちっちゃ、と思ったのでした。
しかし、「京伝賛遊女図」「大原女」などの筆の速い勢いにみえる画力の突き抜けた巧みっぷりには
うなるしかありませんでした。
あっさりと山東京伝が粋に賛を書いているところもツボです。
渓斎栄泉の危険度爆発の妖艶な美人図には吸い寄せられました。
井特の軸には「せいとく」とひらがなで愛らしい印が押してありました。
井特の描く美人の唇は「笹紅」で黒光りしています。
一度見たら忘れられない謎めいた雰囲気のある井特作品を5点も
所有しているとは、感服致しました。
最後に暁斎の「一休禅師地獄太夫図」
小林清親の「頼豪阿闍梨」「祭芸者図」がつんとやられました。
それと特筆すべきはどの軸装にも艶やかな布が使用されていて、
主人公の美人図をより一層賑々しく飾り、華やかにしているところです。
三幅揃い雪月花のデザイン化された表装にはうなりました。
こういった表装デザインにもぜひ注目して欲しいものです。
知らなかった絵師の名前も現れ、ほう、こんな絵師もいたのかと
初見にドキドキしました。
こうなると、漆器、印籠コレクションもぜひに日本へ渡ってきて欲しいものです。
今年ラストの強烈パンチでした。
ひたすら素晴らしかったです。図録も見やすくて秀逸でした。
この展覧に併せて上野の森美術館所蔵
「江戸から東京へ浮世絵版画展」も開催中です。
肉筆画の半券があれば半額、百円で鑑賞できます。
小林清親や、笠松紫浪の作品の魅力もぜひ。
しつこく、1月17日までです。
![]()
4 杉本博司 趣味と芸術ー味占郷
今昔三部作 千葉市美術館
杉本氏の放つ趣味の世界に溺れに行くつもりで初日に出かけました。
その感想は既にブログ記事に書き連ねましたが、
やはりこの人の毒にわざわざやられに行こうと想う人は
ずぶずぶと信徒にならざるを得ないと実感して参りました。
もともと古美術、骨董が好き、なので床飾りに選ばれた品々に
いちいちため息を漏らしてきました。
時代の先端を行く芸術家、写真家かとおもいきや、
小料理屋のオヤジになりきり、
はたまたガラス作家なり
須田悦弘さんとのコラボを楽しみ、
文楽界とも交遊し、茶人若宗匠とも近く、
こんな酔狂をあっさりとやり遂げる人の魅力は
きっと嫉妬の渦にじりじりする御仁もいらっしゃるのではと
それを思うほど、憎たらしくも跪くしかないのです。
作家でもあり、名プロデューサーでもある、
なんとはなしに、デュシャンよりも光悦的な好々爺を思うのでした。
若いお兄さんより、ずっと色気を感じます。
床飾りにはいちいちため息を漏らしてきました。
降参です。
![]()
3 画鬼暁斎 幕末明治の絵師と弟子コンドル
三菱一号館美術館
2015年ほど暁斎作品を間近に見た年は無かったのではないかと思います。
ダブルインパクト展から、うらめしや展の芸大美からトーハクでも巨大地獄図が現れました。
その暁斎の弟子、コンドルが建築した三菱一号館での
暁斎展開催はとても意義深いと思いました。
二人の師弟関係をスケッチやコンドルの画力の上達ぶりを見て
幸福な関係を気づいていったことを知りました。
メトロポリタン美術館からの出品作品を鑑賞する機会も
大変ありがたく、本当に描く事への執心ぶりを見せつけられました。
今年特筆すべき、春画の扱いもこの展覧で一工夫がありました。
暁斎の絵を描くことの楽しさ、自分の腕が試される心地よさ、
可愛い弟子が育ってくれる喜び、
そういった素直な気持ちが超絶技巧の底力になっているのだと
ともかく文句なく上手い初期の作品から頂点の作品などを通して見ることができ、
前期後期と通う楽しみも味わったありがたい展覧会でした。
今後も注目し続けていきたい、絵の巧さが際立つ暁斎、万歳でした。
2 蔡國強 帰去来 横浜美術館
蔡國強の迫力と大画面、花火の放つ瞬間の爆発の燃えた形跡が
絵画となって、見る人を惹きつけてやみません。
大きなスケール感は他の追随をみないのではないかと思います。
横浜美術館というホールの広い天井と展示室の環境と
作品がぴったりとコラボして素晴らしい空中を演出していました。
中国で生まれたという出自と日本で暮らした経験と、
そのアイデンティティの揺らぎこそが
帰去来となって無常観とそれでも生きていく命讃歌へと
導かれていくようでした。
手元で小さくなっている現実から天井を仰ぎ見て
世界はずっと広々としていることに気づき、
打ちひしがれていても前を向けば良いことが見つかるかも知れない、
そんなことを思った気持ちの吹っ切れ感が大いに救われたのでした。
オオカミたちのエンドレスな壁付きは勇ましく切なく、愛おしい作品でした。
破裂の中の愛おしさがふんだんに盛り込まれていることに安堵も覚えたのでした。
新作の春画は未成年達には見られないような工夫がされましたが、
ひたすら愛の讃歌、命の讃歌で毒気を感じられるものではありませんでした。
大げさな表現のようでいて、実はその裏に大変な精密な工芸と
それを支えている大勢の参加者がいたことも忘れられません。
また、横浜美術館特集の戦争テーマも秀逸でした。
インパクト絶大でスケール感が際立っていました。
1 生誕二百年 同い年の若冲と蕪村 サントリー美術館
光琳が亡くなった1716年奇しくも同じ年に生まれた
若冲と蕪村、その二人の回顧展がサントリー美術館で開催されました。
すでに若冲の人気は不動のものとなって、展覧会に若冲の作品が出品されれば
その展覧会の目玉スター的存在となっているのではないでしょうか。
対する蕪村、文人画と俳人としての渋さが鈍く光る玄人な雰囲気です。
その二人がなんと、京都の四条通の間近に暮らしていたそうです。
そういった生活環境からも鑑賞の視点を向け、
二人を対比させて制作された京都の豊かな環境、懐の深さ、
絵師が受け入れられてきた時代などを感じる贅沢な展覧会でした。
展示作品数の多さから展示替えがありましたが
何度となく通いたくなる魅力に引き込まれました。
会場では若冲と蕪村が併走してユニークな若冲、しっとり情感のある蕪村、
画法の違いもわかりやすく、執着度の高い若冲に対し、
さらりと筆が滑る蕪村に改めて惹かれる思いがしました。
ほぼ時系列に展示される中で、影響のあった中国、朝鮮絵画も紹介され、
まさに彼らはこの時代に生々しく生きてきたのだ、という実感を得られるようでした。
近所に住まいながらも二人は交流していたかどうか、
若冲は、俳諧に興味が無く、放浪の蕪村とは交流する手立てもなく、
記録がなかっただけなのかも知れません。
交遊関係者の参加も楽しいものでした。
老練の翁の時代、二人は旺盛な制作意欲を見せます。
若冲が密度の濃い、濃密な作品を次々と描き、
蕪村もまた硬筆なしっかりとした山水画を描いてきた若いころと競べても
まったく衰えを知らず、見る人の目を留める、迫力溢れる作品を次々と発表していきます。
ジャクソン展と親しまれた展覧会、
今回は蕪村にすっかり心奪われ、こんなにステキな絵師だったのかと
驚きを持って感嘆したのでした。
サントリー美術館の展覧に対する真摯な企画と会場デザインには毎回気持ちの良い
鑑賞環境を整えてくれ、サントリー美会員としても信頼し続けられる美術館です。
道八、乾山、藤田美術館、久隅守景、続々と素晴らしい展覧を楽しんだ一年でした。
以上、ようやく2015年ベストをあげましたが、記憶に残ったもの、もう少し
次回書き出したいと思っています。